百合が咲いています。

百合の花は一段と豪華ですね。
さて、今日は父の月命日です。
父は平成28年(2016)8月19日に78歳で亡くなりました。間もなく3年の月日が経とうとしています。「石の上にも三年」とは言いますが、住職としてもまだまだ父には及びません。
亡くなって百箇日が過ぎた頃(2016年11月)、『虚空』という詩誌に、父との思い出(「菩薩行」)を書かせていただきました(52号)。
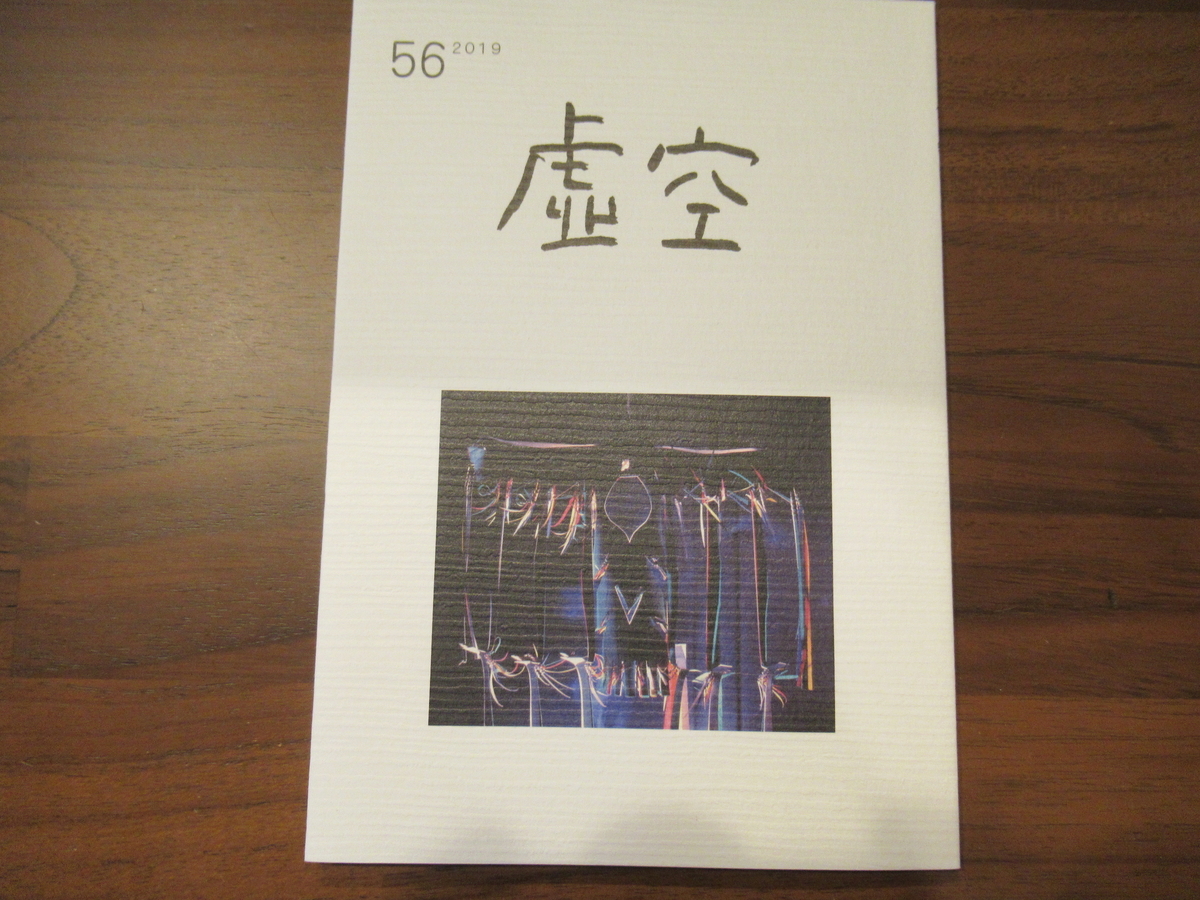
一周忌や初盆に配らせていただきました。多くの方に読んでいただけて、良い供養になったと思っています。
名前だけですが、白川正芳氏(文芸評論家)に取り上げていただいたのも有り難く思いました(「週間読書人」第3184号)。
※ ※
菩薩行
「辯天(べんてん)って酒は旨いんだよなぁ」
一日の終わりに、ふと父が呟(つぶや)いた。日本酒がさほど好きでもなかった私は、ろくに受け答えもせずに、ただ上の空に聞いていた。それはもう二十数年前の、何気ない日常の一齣(ひとこま)だったように思う。
寺の住職でもあった父は、来客があると時折酒を酌み交わしていた。楽しげに笑っているかと思うと、何か議論でもしていたのだろうか、まるで言い争うような大音声が居間にまで響いてくる。しばらくして醉客(すいかく)が帰路につくと、静まり返った家の中で、父の気分はそのままに、
「人生はこんなもんだよ」
などと話しかけてくる夜もあった。私は醉った父の言葉に関心を示すこともなく、「そんなものか」と、いつものように聞き流していた。
今年の夏に父が亡くなった。七十八歳だった。ここ数年は、手術のために入退院を繰り返し、大好きな酒も断っていた。命の灯火(ともしび)が弱まるのを感じてはいたものの、こんなに早く逝ってしまうとは……慌ただしく葬儀を済ませ、瞬く間に四十九日も過ぎていった。
父はどこに行ってしまったのだろう、などと取り留めもないことを考えながら、さまざまな面影が蘇っては消えた。そんな時、ふと思い浮かんだのは、かつて笑顔で語ってくれた冒頭の一言だった。
「辯天って酒は旨いんだよなぁ」
十月下旬のとある秋晴れの日、私は宇都宮駅から下りの新幹線に乗り込んだ。いつも使う東京行きのホームが向かいに見える。不思議な感覚に駆られながら、山形行きの列車は定刻通りに発車した。辯天を造る酒蔵への旅の始まりである。
郡山、福島を過ぎると、一気に奥深い山へと分け入っていった。トンネルを抜けるたびに紅や黄色に染め上げられた木の葉が、枝もたわわに実るリンゴとともに、鮮やかに目に飛び込んでくる。携帯電話も通じない区間を走りながら、「昔はどうやって峠を越えたのだろう」などと思いを馳せていた。
一時間ほどして車窓からの眺めが一変し、開けた土地となった。山形県だ。私は身支度を調え、米沢駅から数分の高畠駅に降り立った。
「ここが辯天の故郷か」
胸が高鳴る。興奮を抑えながら、駅の観光案内所で後藤酒造店への道順を尋ねると、地図を広げて懇切丁寧に教えてくれた。交通量の多い羽州街道を進み、いよいよ最上川が見えてきたとき、江戸時代末期の庄内藩士、清河八郎(きよかわはちろう)(1830~1863)の旅日記『西遊草(さいゆうそう)』の一節が脳裏に浮かんだ。
私は米沢という所について海に遠く山の中の狭い土地だと思っていたが、意外な平地で大そう広い。(中略)人は皆穏かな気立てで、旅行するのに心配なことは何もない。(『西遊草』)
まさに、百六十年ほど前の旅と同じ光景、同じ体験だった。広々とした米沢平野の田面が続き、かつて最上川舟運の最終舟着き場が眼下に見渡せる。糠野目橋(ぬかのめばし)を渡り、旧道に沿ったかつての武家集落に入ると、時を経た「辯天」の木製看板が見えてきた。
天明八年(1788)創業の酒蔵はひっそりと佇んでいた。辯天の起源は、創業者が蔵近くで辯財天(べんざいてん)を祀(まつ)っている奥津島神社(おきつしまじんじゃ)から「辯天」を名乗ることを許されたからとか。裏手に回ってみると、神社は今も厳かに鎮座していた。由緒の案内板に目をやると、
当時は、弁財天宮と尊称しておりましたが、文化六年(1809)市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)を祭神とする奥津島明神(おきつしまみょうじん)と改称し……
とあった。「ここは、ずっと女神に守られてきた土地だ」と深く拝しながら、しばし神酒(しんしゅ)「辯天」の源泉の空気に身を浸していた。
急ぎ駅へと戻り、売店でお目当てのものを探す。
「あった!」
棚に飾られていた四合瓶を胸に抱え、父への家苞(いえづと)とした。
帰りの列車に飛び乗ると、辺りは秋の夕陽に照らされていた。幾重にも重なる山並みが、遙か彼方まで燃えるように色づいている。車窓に映る私の顔も、茜色に染まっていただろう。ただ、刻一刻と夕闇が迫ってきても、私の心の高揚は抑えることができなかった。
家に辿り着くと、父に「辯天」を供えた。そしておもむろに手にとって封を切ると、杯(さかずき)に注いで手に取った。
「献杯(けんぱい)」
口に含み、ゆっくりと喉の奥に流し込むと、身体に熱く沁みていくのを感じた。
「これが旨い酒なんだな」
再びなみなみと注ぎ、幾度となく飲み干し、辯天様の奏でる琵琶のたおやかな音色に身を任せながら、矢継ぎ早に父に語りかけた。
「この酒はどこで飲んだの。久々の辯天は旨いでしょ」
「うちの寺にも、辯天様が祀られてるよね」
「最後に日本酒を口にしたのは、俺の結婚式で交わした固めの杯だったかな」
もちろん一言の返事もない。「今夜はこのまま酔いつぶれてもいい」。そう思ったとき、懐かしい父の声が聞こえた。
「もう今日は止めとけ。焦んなくても、これからの人生で本当の旨さが分かるから」
「……ああ」
私は静かに杯を置いた。不意に父がかつて詠んだ俳句が口をついて出た。
酒も又 菩薩行(ぼさつぎょう)なり 春灯下(しゅんとうか)
「『菩薩行』って何なのかな」
父の言葉と人生を、ぐっと噛み締める月下の独酌(どくしゃく)であった。
(2016年11月)
※ ※
最後までお読みくださりありがとうございました。